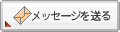沖縄の風景:読者登録
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
沖縄の風景:ブログ検索
沖縄の風景:最近の記事
沖縄の風景:カテゴリー
◆沖縄の風景:全般 (0)
└
イベント・お知らせ (219)
└
お世話になってます (36)
└
深い話 (16)
└
コレやりたい! (9)
└
タメになる?話 (14)
└
ホテル・宿の情報 (27)
└
本の感想 (35)
└
気になるモノ (5)
└
笑える話 (28)
└
雑談 (78)
└
どうでもいい話 (17)
◆沖縄の風景:本島北部 (0)
└
名護市 (14)
└
国頭村 (6)
└
大宜味村 (4)
└
東村 (3)
└
今帰仁村 (44)
└
本部町 (20)
└
恩納村 (25)
└
宜野座村 (2)
└
金武町 (6)
└
伊江村 (27)
└
伊平屋村 (38)
└
伊是名村 (15)
◆沖縄の風景:本島中部 (0)
└
宜野湾市 (40)
└
沖縄市 (35)
└
うるま市 (37)
└
読谷村 (13)
└
嘉手納町 (25)
└
北谷町 (16)
└
北中城村 (33)
└
中城村 (23)
└
西原町 (12)
◆沖縄の風景:本島南部 (0)
└
那覇市 (163)
└
浦添市 (17)
└
糸満市 (9)
└
豊見城市 (8)
└
南城市 (51)
└
与那原町 (1)
└
南風原町 (18)
└
渡嘉敷村 (14)
└
座間味村 (12)
└
粟国村 (49)
└
渡名喜村 (20)
└
南大東村 (24)
└
北大東村 (39)
└
久米島町 (25)
└
八重瀬町 (13)
◆沖縄の風景:宮古 (0)
└
宮古島市 (132)
└
宮古島市伊良部 (38)
└
多良間村 (15)
◆沖縄の風景:八重山 (0)
└
石垣市 (20)
└
竹富町 (26)
└
与那国町 (59)
◆沖縄の風景?:県外 (0)
└
東京都 (82)
└
神奈川県 (22)
└
大阪府 (6)
└
京都府 (2)
└
兵庫県 (10)
└
山口県 (2)
└
福岡県 (20)
└
佐賀県 (11)
└
長崎県 (19)
└
熊本県 (6)
└
大分県 (6)
└
宮崎県 (6)
└
鹿児島県 (2)
└
グァム (6)
└
香港 (16)
沖縄の風景:コメント
沖縄の風景 はじめ / 県営南風原団地建替工事(第2・・・
県営南風原団地建替工事(第2期) / 県営南風原団地建替工事(第2・・・
檸檬 / さわふじの風景
沖縄の風景 はじめ / 安国山樹華木之記碑、南風原・・・
美江 / 安国山樹華木之記碑、南風原・・・
沖縄の風景 はじめ / 安心格安車検、沖縄の車検は・・・
stranger / 安心格安車検、沖縄の車検は・・・
沖縄の風景 はじめ / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
美江 / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
美江 / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
沖縄の風景 はじめ / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
美江 / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
沖縄の風景 はじめ / 竹富島、オシャレな外観の竹・・・
美江 / 竹富島、オシャレな外観の竹・・・
沖縄の風景 はじめ / 石垣港離島ターミナルから竹・・・
沖縄の風景:カウンター
沖縄の風景:タグクラウド
那覇市
宮古島市
モブログ
東京都
与那国町
南城市
今帰仁村
粟国村
宜野湾市
北大東村
うるま市
伊平屋村
沖縄市
琉球ドラゴンプロレス
伊良部島
世界遺産
琉球ドラゴンプロレスリング
北中城村
那覇空港
竹富町
竹富島
伊江村
天然記念物
文化財
石垣市
拝所
南大東村
恩納村
沖縄キャンプ
台風
今帰仁城跡
久米島町
鍾乳洞
嘉手納町
南風原町
本部町
首里城公園
渡名喜村
琉球石灰岩
中城村
台風対策
台風情報
パワースポット
テオ・ヤンセン
ビーチアニマル
宝当神社
玉泉洞
渡嘉敷村
香港
福岡県
伊良部大橋
首里城
名護市
浦添市
北谷町
琉球ゴールデンキングス
ユネスコ
天気予報
伊是名村
国際通り
プロ野球
栗城史多
宿泊施設
長崎市
佐賀県
Dr.コトー診療所
宝くじ
座間味村
池間島
八重瀬町
沖縄県立博物館
重要文化財
有形文化財
さしみ屋
刺身屋
台風予報
ネーブルカデナアリーナ
ストランドビースト
テオヤンセン
読谷村
古宇利島
神奈川県
多良間村
さしみ屋のお告げ
沖縄県
西原町
日本トランスオーシャン航空
宮古島
奥武島
琉球キングス
琉球王国のグスク及び関連遺産群
豊見城市
粟国の塩
広島東洋カープ
興南高校
グルクンマスク
琉球ドラゴンチャンプルー
沖縄県立美術館
観光名所
湧水
沖縄の風景:過去記事
悲風の丘の風景(その3)
>> 悲風の丘の風景(その1)
>> 悲風の丘の風景(その2)はこちら
まずい、道がない!

まずい、道がない!

道を見失って慌てましたが、しばらくうろうろしているうち、仏ぬ前の石碑があった場所まで戻ってこれました。

ちょっと慌てましたが、気を取り直して先へ進みます。

道を見つけたのはいいのですが、だんだん勾配がついて急な下りになってきたので、何度も滑り落ちそうになります。

何度も足を取られそうになりながらも前へ進んでいくと、それを見越していたか、道沿いにガイドロープが張り巡らされていました。ここから先はロープをつかみながら、ゆっくりと前へ進みます。

しばらくすると道らしい道がなくなってくるのですが、誘導の看板がいくつかありましたので、それを頼りに進んでいきます。

またしばらく進んでいくと、目の前に憲法九条の碑が見えてきました!

飯あげの道は24号壕の前に出てくるようになっていました。

 沖縄陸軍病院24号壕(第1外科壕群) - 現地の看板より引用
沖縄陸軍病院24号壕(第1外科壕群) - 現地の看板より引用
24号壕は貫通していない未完成の壕です。当時は滴がしたたり、中はぬかるんでいました。ひめゆり学徒隊70人~80人の待機所となってからも、壕の奥では壕掘り作業が続き、落盤の危険があったのです。酸素が減ってろうそくの炎が消えそうになると、上着や風呂敷、毛布などを振って中の空気を入れ換えました。1945年(昭和20年)4月末には、患者の病室として使用することになりました。
現在の24号壕は幅が床面1.8メートル、天井部1.6メートル、高さは1.8メートルで、壁面には約90センチおきに坑木を立てた跡があります。中に入って約32メートルほぼ真っ直ぐに進み、左に曲がると4メートルほどで行き止まりです。しかし、そこから23号壕に下りる幅1メートルの細い通路が掘られています。現在の出入り口は、崩れてきた天井の土によって高い位置になっており、本来の出入り口はもう少し前方であったようです。
南風原文化センター 2002年
24号壕の入り口は、崩れてきた天井の土でほとんど塞がっているように見えます。

飯あげの道を抜けると、目の前に20号壕入り口の管理棟が見えます。

山道に慣れている方なら、これくらいのけもの道なんて大したことないかと思います。
しかし当時は、砲弾が頭の上を飛び交う中、ひめゆり学徒隊の方は壕から井戸のある炊事場まで、炊き出しのため天秤棒を担いでこの道を行き来していたと言われています。壕の入り口から、丘の向こうにいる米兵の姿が見えたという証言もあるそうですので、本当に命がけの作業だったと思います。
壕には直視出来ないほどの重傷患者が次々と運び込まれ、出来る治療といえば傷口からの炎症を防ぐため、その手足を切断するための患部手術のみ。ほとんどの手術は麻酔なしで行われるため、ひめゆり学徒隊の方が出来ることといえば数人がかりで暴れる患者を押さえつけること。患者の包帯を取り替えるときに行うのは、傷口にわいたウジを取り除くことと多量の膿を拭き取ること。壕の中には昼夜を問わずうめき声が響き渡り、交代制で砲弾が飛び交う中を天秤棒を担いで炊き出しに走る。
生き地獄です。
ひめゆり学徒隊の方は当時、どんな気持ちでこのけもの道を行き来していたのか、正直なところ想像すらつきません。

「沖縄の風景」いかがでしたか?
気に入って頂けましたら、こちらをポチッとクリックお願いします!
>> 悲風の丘の風景(その2)はこちら
まずい、道がない!
まずい、道がない!
道を見失って慌てましたが、しばらくうろうろしているうち、仏ぬ前の石碑があった場所まで戻ってこれました。
ちょっと慌てましたが、気を取り直して先へ進みます。
道を見つけたのはいいのですが、だんだん勾配がついて急な下りになってきたので、何度も滑り落ちそうになります。
何度も足を取られそうになりながらも前へ進んでいくと、それを見越していたか、道沿いにガイドロープが張り巡らされていました。ここから先はロープをつかみながら、ゆっくりと前へ進みます。
しばらくすると道らしい道がなくなってくるのですが、誘導の看板がいくつかありましたので、それを頼りに進んでいきます。
またしばらく進んでいくと、目の前に憲法九条の碑が見えてきました!
飯あげの道は24号壕の前に出てくるようになっていました。
 沖縄陸軍病院24号壕(第1外科壕群) - 現地の看板より引用
沖縄陸軍病院24号壕(第1外科壕群) - 現地の看板より引用24号壕は貫通していない未完成の壕です。当時は滴がしたたり、中はぬかるんでいました。ひめゆり学徒隊70人~80人の待機所となってからも、壕の奥では壕掘り作業が続き、落盤の危険があったのです。酸素が減ってろうそくの炎が消えそうになると、上着や風呂敷、毛布などを振って中の空気を入れ換えました。1945年(昭和20年)4月末には、患者の病室として使用することになりました。
現在の24号壕は幅が床面1.8メートル、天井部1.6メートル、高さは1.8メートルで、壁面には約90センチおきに坑木を立てた跡があります。中に入って約32メートルほぼ真っ直ぐに進み、左に曲がると4メートルほどで行き止まりです。しかし、そこから23号壕に下りる幅1メートルの細い通路が掘られています。現在の出入り口は、崩れてきた天井の土によって高い位置になっており、本来の出入り口はもう少し前方であったようです。
南風原文化センター 2002年
24号壕の入り口は、崩れてきた天井の土でほとんど塞がっているように見えます。
飯あげの道を抜けると、目の前に20号壕入り口の管理棟が見えます。
山道に慣れている方なら、これくらいのけもの道なんて大したことないかと思います。
しかし当時は、砲弾が頭の上を飛び交う中、ひめゆり学徒隊の方は壕から井戸のある炊事場まで、炊き出しのため天秤棒を担いでこの道を行き来していたと言われています。壕の入り口から、丘の向こうにいる米兵の姿が見えたという証言もあるそうですので、本当に命がけの作業だったと思います。
壕には直視出来ないほどの重傷患者が次々と運び込まれ、出来る治療といえば傷口からの炎症を防ぐため、その手足を切断するための患部手術のみ。ほとんどの手術は麻酔なしで行われるため、ひめゆり学徒隊の方が出来ることといえば数人がかりで暴れる患者を押さえつけること。患者の包帯を取り替えるときに行うのは、傷口にわいたウジを取り除くことと多量の膿を拭き取ること。壕の中には昼夜を問わずうめき声が響き渡り、交代制で砲弾が飛び交う中を天秤棒を担いで炊き出しに走る。
生き地獄です。
ひめゆり学徒隊の方は当時、どんな気持ちでこのけもの道を行き来していたのか、正直なところ想像すらつきません。

「沖縄の風景」いかがでしたか?
気に入って頂けましたら、こちらをポチッとクリックお願いします!
この記事へのコメント
ひめゆりの生存者の証言、まさに生き地獄だったといってました。想像を絶するものがあります
Posted by 美江 at 2008年06月25日 09:11
at 2008年06月25日 09:11
 at 2008年06月25日 09:11
at 2008年06月25日 09:11
やはりここは
行かないといけませんね~
しかしながら
身体が持つかどうか。。。
だんだん身体が重くなるので^^
行かないといけませんね~
しかしながら
身体が持つかどうか。。。
だんだん身体が重くなるので^^
Posted by TADARIN at 2008年06月26日 08:00
at 2008年06月26日 08:00
 at 2008年06月26日 08:00
at 2008年06月26日 08:00
いやいや生還できてよかったです。(^^)
しかし、ダメですよ。
森に入る時は、目印にパンくずを落としていかなくては。笑
戦時中の話は、私も年配のスタッフからたまに聞くことがありますが、
今後のためにも、語り継いでいかなければ、なりませんね。
しかし、ダメですよ。
森に入る時は、目印にパンくずを落としていかなくては。笑
戦時中の話は、私も年配のスタッフからたまに聞くことがありますが、
今後のためにも、語り継いでいかなければ、なりませんね。
Posted by tasa at 2008年06月27日 14:11
いや~、読んでいるうちに、想像して怖くなりましたよ~。
生きるか死ぬかの中で生きると言う感覚が全く想像つきません。
それにしてもその行動力、ただただ脱帽です。
生きるか死ぬかの中で生きると言う感覚が全く想像つきません。
それにしてもその行動力、ただただ脱帽です。
Posted by ウイング at 2008年06月28日 10:08
at 2008年06月28日 10:08
 at 2008年06月28日 10:08
at 2008年06月28日 10:08
ハイサイ、はじめさん。いつもすごい取材にはびっくりしています。
なかなか、自分のブログをひらく事もないもので、一月遅れの返事になってしまいました。すみません。
沖縄では、蘇鉄は首里城の非常食ではなく、庶民の食料だったのですね。
なぜか?……、それにもまた、深い歴史上のがあるんですよ。
なかなか、自分のブログをひらく事もないもので、一月遅れの返事になってしまいました。すみません。
沖縄では、蘇鉄は首里城の非常食ではなく、庶民の食料だったのですね。
なぜか?……、それにもまた、深い歴史上のがあるんですよ。
Posted by 長田社長 at 2008年06月29日 23:09
道がないとこを歩いて
道を作っていくのですね~、
高村光太郎みたいです。
こんな大変な道のりを歩いて戦争体験者の
気持ちに沿う…はじめさんは優しい方だ!
道を作っていくのですね~、
高村光太郎みたいです。
こんな大変な道のりを歩いて戦争体験者の
気持ちに沿う…はじめさんは優しい方だ!
Posted by 三角食堂 at 2008年06月30日 08:04
美江さんこんにちは。
生存者の証言を聞かれたのですね。
今回、飯あげの道を実際に辿ってみながら、
もし、頭の上を砲弾が飛んでいったら....
もし、丘の向こうに米兵の姿が見えたら....
自分は本当にここを歩けるのだろうかと、
いろいろ考えさせられました。
生存者の証言を聞かれたのですね。
今回、飯あげの道を実際に辿ってみながら、
もし、頭の上を砲弾が飛んでいったら....
もし、丘の向こうに米兵の姿が見えたら....
自分は本当にここを歩けるのだろうかと、
いろいろ考えさせられました。
Posted by はじめ at 2008年07月02日 12:40
at 2008年07月02日 12:40
 at 2008年07月02日 12:40
at 2008年07月02日 12:40
TADARINさんこんにちは。
体が重くならないうちに、
ぜひ悲風の丘をご覧下さい。(笑)
ただ最近、雰囲気が変わっていますので、
この画像の通りではないと思います。
体が重くならないうちに、
ぜひ悲風の丘をご覧下さい。(笑)
ただ最近、雰囲気が変わっていますので、
この画像の通りではないと思います。
Posted by はじめ at 2008年07月02日 12:43
at 2008年07月02日 12:43
 at 2008年07月02日 12:43
at 2008年07月02日 12:43
tasaさんこんにちは。
目印でところどころ草を結んではいたのですが.... (笑)
正直、戦争の話は怖くて聞きたくないこともあるのですが、
忘れる訳にはいかないと思っています。
目印でところどころ草を結んではいたのですが.... (笑)
正直、戦争の話は怖くて聞きたくないこともあるのですが、
忘れる訳にはいかないと思っています。
Posted by はじめ at 2008年07月02日 12:52
at 2008年07月02日 12:52
 at 2008年07月02日 12:52
at 2008年07月02日 12:52
ウイングさんこんにちは。
道そのものは大したことなかったのですが、
その背景を知っていただけに、
歩きながらいろいろ考えてしまいました。
生きるか死ぬかの瀬戸際。
当時の戦争体験者は大変だったと、
口で言うのは簡単ですが、
私もその状況は想像すらできません。
道そのものは大したことなかったのですが、
その背景を知っていただけに、
歩きながらいろいろ考えてしまいました。
生きるか死ぬかの瀬戸際。
当時の戦争体験者は大変だったと、
口で言うのは簡単ですが、
私もその状況は想像すらできません。
Posted by はじめ at 2008年07月02日 13:06
at 2008年07月02日 13:06
 at 2008年07月02日 13:06
at 2008年07月02日 13:06
長田所長こんにちは。
自分では取材という感覚はなくて、
単なる"見たがり屋"です.... (汗)
首里城のソテツが庶民の食料であった件ですが、
その背景に興味がありますので、
いつかまた紹介して下さい!
自分では取材という感覚はなくて、
単なる"見たがり屋"です.... (汗)
首里城のソテツが庶民の食料であった件ですが、
その背景に興味がありますので、
いつかまた紹介して下さい!
Posted by はじめ at 2008年07月02日 13:15
at 2008年07月02日 13:15
 at 2008年07月02日 13:15
at 2008年07月02日 13:15
魔法の三角食堂さんこんにちは。
高村光太郎なんて、とてもとても.... (汗)
道そのものは大したことなかったのですが、
何もない静かな道を淡々と歩いていると、
もし、頭の上から砲弾が飛んでいったら....
もし、自分を狙っている兵隊が丘の向こうに見えたら....
いろいろと想像してしまい、
もの凄い恐怖感に襲われました。
当時の方がこの道をどんな気持ちで行き来したのか、
やっぱり私は想像すらつきません。
高村光太郎なんて、とてもとても.... (汗)
道そのものは大したことなかったのですが、
何もない静かな道を淡々と歩いていると、
もし、頭の上から砲弾が飛んでいったら....
もし、自分を狙っている兵隊が丘の向こうに見えたら....
いろいろと想像してしまい、
もの凄い恐怖感に襲われました。
当時の方がこの道をどんな気持ちで行き来したのか、
やっぱり私は想像すらつきません。
Posted by はじめ at 2008年07月02日 13:23
at 2008年07月02日 13:23
 at 2008年07月02日 13:23
at 2008年07月02日 13:23
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。