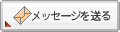沖縄の風景:読者登録
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
沖縄の風景:ブログ検索
沖縄の風景:最近の記事
沖縄の風景:カテゴリー
◆沖縄の風景:全般 (0)
└
イベント・お知らせ (219)
└
お世話になってます (36)
└
深い話 (16)
└
コレやりたい! (9)
└
タメになる?話 (14)
└
ホテル・宿の情報 (27)
└
本の感想 (35)
└
気になるモノ (5)
└
笑える話 (28)
└
雑談 (78)
└
どうでもいい話 (17)
◆沖縄の風景:本島北部 (0)
└
名護市 (14)
└
国頭村 (6)
└
大宜味村 (4)
└
東村 (3)
└
今帰仁村 (44)
└
本部町 (20)
└
恩納村 (25)
└
宜野座村 (2)
└
金武町 (6)
└
伊江村 (27)
└
伊平屋村 (38)
└
伊是名村 (15)
◆沖縄の風景:本島中部 (0)
└
宜野湾市 (40)
└
沖縄市 (35)
└
うるま市 (37)
└
読谷村 (13)
└
嘉手納町 (25)
└
北谷町 (16)
└
北中城村 (33)
└
中城村 (23)
└
西原町 (12)
◆沖縄の風景:本島南部 (0)
└
那覇市 (163)
└
浦添市 (17)
└
糸満市 (9)
└
豊見城市 (8)
└
南城市 (51)
└
与那原町 (1)
└
南風原町 (18)
└
渡嘉敷村 (14)
└
座間味村 (12)
└
粟国村 (49)
└
渡名喜村 (20)
└
南大東村 (24)
└
北大東村 (39)
└
久米島町 (25)
└
八重瀬町 (13)
◆沖縄の風景:宮古 (0)
└
宮古島市 (132)
└
宮古島市伊良部 (38)
└
多良間村 (15)
◆沖縄の風景:八重山 (0)
└
石垣市 (20)
└
竹富町 (26)
└
与那国町 (59)
◆沖縄の風景?:県外 (0)
└
東京都 (82)
└
神奈川県 (22)
└
大阪府 (6)
└
京都府 (2)
└
兵庫県 (10)
└
山口県 (2)
└
福岡県 (20)
└
佐賀県 (11)
└
長崎県 (19)
└
熊本県 (6)
└
大分県 (6)
└
宮崎県 (6)
└
鹿児島県 (2)
└
グァム (6)
└
香港 (16)
沖縄の風景:コメント
沖縄の風景 はじめ / 県営南風原団地建替工事(第2・・・
県営南風原団地建替工事(第2期) / 県営南風原団地建替工事(第2・・・
檸檬 / さわふじの風景
沖縄の風景 はじめ / 安国山樹華木之記碑、南風原・・・
美江 / 安国山樹華木之記碑、南風原・・・
沖縄の風景 はじめ / 安心格安車検、沖縄の車検は・・・
stranger / 安心格安車検、沖縄の車検は・・・
沖縄の風景 はじめ / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
美江 / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
美江 / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
沖縄の風景 はじめ / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
美江 / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
沖縄の風景 はじめ / 竹富島、オシャレな外観の竹・・・
美江 / 竹富島、オシャレな外観の竹・・・
沖縄の風景 はじめ / 石垣港離島ターミナルから竹・・・
沖縄の風景:カウンター
沖縄の風景:タグクラウド
那覇市
宮古島市
モブログ
東京都
与那国町
南城市
今帰仁村
粟国村
宜野湾市
北大東村
うるま市
伊平屋村
沖縄市
琉球ドラゴンプロレス
伊良部島
世界遺産
琉球ドラゴンプロレスリング
北中城村
那覇空港
竹富町
竹富島
伊江村
天然記念物
文化財
石垣市
拝所
南大東村
恩納村
沖縄キャンプ
台風
今帰仁城跡
久米島町
鍾乳洞
嘉手納町
南風原町
本部町
首里城公園
渡名喜村
琉球石灰岩
中城村
台風対策
台風情報
パワースポット
テオ・ヤンセン
ビーチアニマル
宝当神社
玉泉洞
渡嘉敷村
香港
福岡県
伊良部大橋
首里城
名護市
浦添市
北谷町
琉球ゴールデンキングス
ユネスコ
天気予報
伊是名村
国際通り
プロ野球
栗城史多
宿泊施設
長崎市
佐賀県
Dr.コトー診療所
宝くじ
座間味村
池間島
八重瀬町
沖縄県立博物館
重要文化財
有形文化財
さしみ屋
刺身屋
台風予報
ネーブルカデナアリーナ
ストランドビースト
テオヤンセン
読谷村
古宇利島
神奈川県
多良間村
さしみ屋のお告げ
沖縄県
西原町
日本トランスオーシャン航空
宮古島
奥武島
琉球キングス
琉球王国のグスク及び関連遺産群
豊見城市
粟国の塩
広島東洋カープ
興南高校
グルクンマスク
琉球ドラゴンチャンプルー
沖縄県立美術館
観光名所
湧水
沖縄の風景:過去記事
糸数アブチラガマで平和について考える(その1)
沖縄の言葉で洞窟や洞穴のことを「ガマ」と呼びます。
南城市玉城に糸数アブチラガマという名前の自然洞窟があります。
第二次世界大戦の沖縄戦では避難壕として使用され、
現在は平和学習や修学旅行の観光コースとして紹介されています。
実は私、恥ずかしながら、
その日までアブチラガマの存在を知りませんでした。
たまたま近くを通りがかったときに看板を見かけ、
単なる興味本位で立ち寄ったのです。
私はアブチラガマについて何の知識もないまま、
中に入ってみることにしました。
近くにある南部観光総合案内センターで入場料200円を支払おうとしたとき、
「懐中電灯は持っていますか?」と聞かれました。
いいえ、と答えると100円で貸し出すとのこと。
別に必要ないだろうと思い断ると、
どうしても持って行くようしつこく薦めてくるので仕方なく借りることに。
懐中電灯と一緒に薦めてきたヘルメットはお断りしました。

 「糸数アブチラガマ(糸数壕)」
「糸数アブチラガマ(糸数壕)」
このガマは全長が約270mに及ぶ自然洞窟で、昭和19年7月頃から日本軍の陣地としての整備が始まった。
昭和20年3月23日本島南部が艦砲射撃を受け、翌24日から糸数住民約200名がこのガマへ避難した。その当時は日本軍の陣地・食料倉庫および糸数住民の避難壕として使用されていた。
その後地上戦が激しくなり本島南部への危険が迫っていた4月下旬頃、南風原陸軍病院の分室として糸数アブチラガマが設定され、5月1日から約600名の患者が担送されてきた。このガマも危険になってきた5月下旬の撤退まで陸軍病院として使用された。病院の撤退後は重症患者が置き去りにされ、米軍からの攻撃もたびたび受け、悲惨を極めた地獄絵が展開された。しかし、このガマのお陰で生き延びた人達がいることも忘れてはならない事実である。
このガマで亡くなられた方々の遺骨は、戦後糸数住民と関係者等により蒐集され、国立沖縄戦没者墓宛に合祀された。
案内センターの駐車場から100mほど歩いたところに、
糸数アブチラガマの入口があります。
あまり目立たないので分かりにくいかも知れません。

受付の方に入場券を渡すと、
受付名簿に名前を記入するよう言われます。
そこまではごく普通の風景ですが....
受付の方が私の書いた名前の横に、
「男性、身長約○○cm、年齢○○代程度」と書き加えたのを見逃しませんでした。
そのときは何故そのようなことまでいちいち書くのか分からなかったのですが、
ガマの中に入ったとき、その理由が分かりました...
アブチラガマの入口はとても小さく、大人がやっと入れるかという程度です。

ガマの入口から中に進んでいくと、
中から蒸し暑い熱気がこみ上げてきます。
もう、とにかく湿気が凄くて、
当時の居心地はかなり悪かっただろうと思われます。

ガマの中に入ったとき、
何故、懐中電灯をしつこく薦めてきたのか、
何故、受付の方が名前の横に私の見た目の特徴を書き加えたのか、
その全ての理由が分かりました...
中は真っ暗で全く何も見えないのです!

ガマの中は一切照明がなく(照明設備はあるが点灯していない。)、
私が受付で借りた小さな懐中電灯では足下を照らすのがやっとという状態で、
とてもガマの全体像を見渡すことは出来ません。
何歩か進んでみたのですが、
真っ暗闇の中で足下だけ心細く照らしているような状況なので、
かなりの恐怖感に襲われます。
写真撮影をするつもりではないのですが、
デジカメのストロボを何度も何度もたき、
その灯りでガマの内部を確認していました。

あまりの恐怖感から汗が背中を伝っているのがはっきりと分かりました。
内部の地図が書かれたパンフレットを持ってきてはいるのですが、
自分が今どこに立っているのかが分からないので殆ど意味をなしません。
暗闇の中でたまに見かける「順路」と書かれた看板だけを頼りに先へ進みます。
人間、こういう状況に置かれると悪い想像ばかり膨らむもので、
「もし看板を見失ったらどうしよう?」、
「もし懐中電灯の電池が切れてしまったらどうしよう?」と、不安は広がるばかりです。
一度引き返そうとしたのですが、
さっき見たはずの順路の看板を見つけることが出来なかったため、
無理に戻ると逆に迷子になってしまうのではないかと考え、
そのまま先へ進むことにしました。
 糸数アブチラガマの場所はこちら。
糸数アブチラガマの場所はこちら。
[糸数アブチラガマ、その他の記事はこちら]
糸数アブチラガマで平和について考える(その2)
「沖縄の風景」いかがでしたか? すべての出愛(出会い)に感謝です。
気に入って頂けましたら、下のボタンをポチッとクリックお願いします!


南城市玉城に糸数アブチラガマという名前の自然洞窟があります。
第二次世界大戦の沖縄戦では避難壕として使用され、
現在は平和学習や修学旅行の観光コースとして紹介されています。
実は私、恥ずかしながら、
その日までアブチラガマの存在を知りませんでした。
たまたま近くを通りがかったときに看板を見かけ、
単なる興味本位で立ち寄ったのです。
私はアブチラガマについて何の知識もないまま、
中に入ってみることにしました。
近くにある南部観光総合案内センターで入場料200円を支払おうとしたとき、
「懐中電灯は持っていますか?」と聞かれました。
いいえ、と答えると100円で貸し出すとのこと。
別に必要ないだろうと思い断ると、
どうしても持って行くようしつこく薦めてくるので仕方なく借りることに。
懐中電灯と一緒に薦めてきたヘルメットはお断りしました。
 「糸数アブチラガマ(糸数壕)」
「糸数アブチラガマ(糸数壕)」このガマは全長が約270mに及ぶ自然洞窟で、昭和19年7月頃から日本軍の陣地としての整備が始まった。
昭和20年3月23日本島南部が艦砲射撃を受け、翌24日から糸数住民約200名がこのガマへ避難した。その当時は日本軍の陣地・食料倉庫および糸数住民の避難壕として使用されていた。
その後地上戦が激しくなり本島南部への危険が迫っていた4月下旬頃、南風原陸軍病院の分室として糸数アブチラガマが設定され、5月1日から約600名の患者が担送されてきた。このガマも危険になってきた5月下旬の撤退まで陸軍病院として使用された。病院の撤退後は重症患者が置き去りにされ、米軍からの攻撃もたびたび受け、悲惨を極めた地獄絵が展開された。しかし、このガマのお陰で生き延びた人達がいることも忘れてはならない事実である。
このガマで亡くなられた方々の遺骨は、戦後糸数住民と関係者等により蒐集され、国立沖縄戦没者墓宛に合祀された。
案内センターの駐車場から100mほど歩いたところに、
糸数アブチラガマの入口があります。
あまり目立たないので分かりにくいかも知れません。
受付の方に入場券を渡すと、
受付名簿に名前を記入するよう言われます。
そこまではごく普通の風景ですが....
受付の方が私の書いた名前の横に、
「男性、身長約○○cm、年齢○○代程度」と書き加えたのを見逃しませんでした。
そのときは何故そのようなことまでいちいち書くのか分からなかったのですが、
ガマの中に入ったとき、その理由が分かりました...
アブチラガマの入口はとても小さく、大人がやっと入れるかという程度です。
ガマの入口から中に進んでいくと、
中から蒸し暑い熱気がこみ上げてきます。
もう、とにかく湿気が凄くて、
当時の居心地はかなり悪かっただろうと思われます。
ガマの中に入ったとき、
何故、懐中電灯をしつこく薦めてきたのか、
何故、受付の方が名前の横に私の見た目の特徴を書き加えたのか、
その全ての理由が分かりました...
中は真っ暗で全く何も見えないのです!
ガマの中は一切照明がなく(照明設備はあるが点灯していない。)、
私が受付で借りた小さな懐中電灯では足下を照らすのがやっとという状態で、
とてもガマの全体像を見渡すことは出来ません。
何歩か進んでみたのですが、
真っ暗闇の中で足下だけ心細く照らしているような状況なので、
かなりの恐怖感に襲われます。
写真撮影をするつもりではないのですが、
デジカメのストロボを何度も何度もたき、
その灯りでガマの内部を確認していました。
あまりの恐怖感から汗が背中を伝っているのがはっきりと分かりました。
内部の地図が書かれたパンフレットを持ってきてはいるのですが、
自分が今どこに立っているのかが分からないので殆ど意味をなしません。
暗闇の中でたまに見かける「順路」と書かれた看板だけを頼りに先へ進みます。
人間、こういう状況に置かれると悪い想像ばかり膨らむもので、
「もし看板を見失ったらどうしよう?」、
「もし懐中電灯の電池が切れてしまったらどうしよう?」と、不安は広がるばかりです。
一度引き返そうとしたのですが、
さっき見たはずの順路の看板を見つけることが出来なかったため、
無理に戻ると逆に迷子になってしまうのではないかと考え、
そのまま先へ進むことにしました。
 糸数アブチラガマの場所はこちら。
糸数アブチラガマの場所はこちら。[糸数アブチラガマ、その他の記事はこちら]
糸数アブチラガマで平和について考える(その2)
「沖縄の風景」いかがでしたか? すべての出愛(出会い)に感謝です。
気に入って頂けましたら、下のボタンをポチッとクリックお願いします!

この記事へのコメント
はじめさん、はじめまして。
足跡からお邪魔しました。
リアルな写真レポートありがとうございます。
私は玉泉洞に行った時に「避難していたガマもこんななのかなぁ…湿気があって大変だっただろうなあ…」と想像するのみでした。
そうか、真っ暗なんですね…
戦争中は灯りはロウソクでしょうか、燈油ランプでしょうか…
電池ランプは当時あったのかな…
なんにせよ換気も悪そうですよね…
足跡からお邪魔しました。
リアルな写真レポートありがとうございます。
私は玉泉洞に行った時に「避難していたガマもこんななのかなぁ…湿気があって大変だっただろうなあ…」と想像するのみでした。
そうか、真っ暗なんですね…
戦争中は灯りはロウソクでしょうか、燈油ランプでしょうか…
電池ランプは当時あったのかな…
なんにせよ換気も悪そうですよね…
Posted by 亜衣 at 2007年08月10日 01:09
at 2007年08月10日 01:09
 at 2007年08月10日 01:09
at 2007年08月10日 01:09
こんにちは!
最後の写真の煙?
白いモヤが中の暑さなど
明かりが無かったら怖いだろうなという
感じが伝わります!(・・;)
1人だったら入りたくないです!(>0<;)
最後の写真の煙?
白いモヤが中の暑さなど
明かりが無かったら怖いだろうなという
感じが伝わります!(・・;)
1人だったら入りたくないです!(>0<;)
Posted by ちかママ&シュウぱぱ at 2007年08月11日 18:13
at 2007年08月11日 18:13
 at 2007年08月11日 18:13
at 2007年08月11日 18:13
亜衣さんこんばんは。
戦時中のガマの中は真っ暗という訳ではなかったと思うのですが、外敵に見つからないようあまり明るくはなかったと思います。いずれにしても居心地は相当悪いですので、そんな中に身を潜めるしかなかった当時の方を思うと悲しくなってきます。
ちかママさんこんばんは。
正直なところ、私ももう一人では入りたくないです。怖いし居心地は悪いし、人間が生活していく上でそこの条件は最低だと思います。
だけどそこに身を潜めるしかなかった方々がいた事実は忘れてはいけないと思います。
戦時中のガマの中は真っ暗という訳ではなかったと思うのですが、外敵に見つからないようあまり明るくはなかったと思います。いずれにしても居心地は相当悪いですので、そんな中に身を潜めるしかなかった当時の方を思うと悲しくなってきます。
ちかママさんこんばんは。
正直なところ、私ももう一人では入りたくないです。怖いし居心地は悪いし、人間が生活していく上でそこの条件は最低だと思います。
だけどそこに身を潜めるしかなかった方々がいた事実は忘れてはいけないと思います。
Posted by はじめ at 2007年08月12日 02:10
at 2007年08月12日 02:10
 at 2007年08月12日 02:10
at 2007年08月12日 02:10
はじめまして、沖縄が好きで、将来は移住を予定している愛知県在住の者です。
本日このブログを初めて拝見しまして、すぐ読者登録しました。これからもいろいろと沖縄情報を御紹介ください。
さて、わたしも南部は割りとよく行ってまして糸数壕も、何回か行ってます。それは、今は手元にありませんが、また書名も記憶にありませんが、(題名にアブチラガマがふくまれていたようにおもいます。)ある本を読んだからで、その記憶によると、ずっと稼動してたわけではないものの、近くに発電小屋や、電灯設備もあったようです。家畜小屋などもあったようです。
現在公開されているのは、全体の約半分です。書名等、調べておきましょうね。あと、お願いなのですが、「南冥の塔」と「轟壕」をとりあげていただけませんか?はじめさんが適役だとおもいます。
平和のためぜひよろしくお願いします。わたしの知るかぎり情報は、提供いたします。
ただ糸数壕は、管理されていますが、轟壕は、糸満市役所に問い合わせると「自己責任でどうぞ」状態ですから、絶対に一人では、入らないでください。最近は入り口の埋まりかかった土はとり除かれコンクリートの階段は作られ、修学旅行の学生さんさえみかけますが、わたしは必ず二人以上で、懐中電灯など2本以上持って入っています。糸数壕のように非常灯などの設備はありません。中は広く井戸、川、池さえあります、ぬかるんでいるところもあります。
ただ、ここは、・・・・・たくさんの方が亡くなっていると、背筋が感じるとおもいますよ。いちど行ってみてください。当時の軍隊と住民の間にいろいろとあった訳ですが、うちなんちゅうにとって耐え難い内容も多い訳ですが、とりあえずはそういう事実があったことを認識していただきたいのです。・・・・・・・ 長くなりました。今度9月に沖縄へいきます。新しい報告ができると思います。
本日このブログを初めて拝見しまして、すぐ読者登録しました。これからもいろいろと沖縄情報を御紹介ください。
さて、わたしも南部は割りとよく行ってまして糸数壕も、何回か行ってます。それは、今は手元にありませんが、また書名も記憶にありませんが、(題名にアブチラガマがふくまれていたようにおもいます。)ある本を読んだからで、その記憶によると、ずっと稼動してたわけではないものの、近くに発電小屋や、電灯設備もあったようです。家畜小屋などもあったようです。
現在公開されているのは、全体の約半分です。書名等、調べておきましょうね。あと、お願いなのですが、「南冥の塔」と「轟壕」をとりあげていただけませんか?はじめさんが適役だとおもいます。
平和のためぜひよろしくお願いします。わたしの知るかぎり情報は、提供いたします。
ただ糸数壕は、管理されていますが、轟壕は、糸満市役所に問い合わせると「自己責任でどうぞ」状態ですから、絶対に一人では、入らないでください。最近は入り口の埋まりかかった土はとり除かれコンクリートの階段は作られ、修学旅行の学生さんさえみかけますが、わたしは必ず二人以上で、懐中電灯など2本以上持って入っています。糸数壕のように非常灯などの設備はありません。中は広く井戸、川、池さえあります、ぬかるんでいるところもあります。
ただ、ここは、・・・・・たくさんの方が亡くなっていると、背筋が感じるとおもいますよ。いちど行ってみてください。当時の軍隊と住民の間にいろいろとあった訳ですが、うちなんちゅうにとって耐え難い内容も多い訳ですが、とりあえずはそういう事実があったことを認識していただきたいのです。・・・・・・・ 長くなりました。今度9月に沖縄へいきます。新しい報告ができると思います。
Posted by kenshin at 2007年08月22日 02:39
kenshinさんこんばんは。
私のブログに興味を持って頂き、ありがとうございます。
糸数アブチラガマにつきましては、今回何の知識もないまま中に入りましたので、私が目で見た範囲の内容しか紹介していません。当時は病院分室として利用されていた程ですので、ご指摘の通りガマの中には様々な施設が存在していたかも知れません。
ただブログにも書きましたが、中は暗く蒸し暑く、本当に居心地の悪いところでした。このような中で過ごさなければならなかった方々が居た事実は忘れてはいけないと思います。
「南冥の塔」と「轟の壕」につきましては、すぐにという訳ではありませんが、機会を見つけ行ってみたいと思います。ご意見ありがとうございました。
私のブログに興味を持って頂き、ありがとうございます。
糸数アブチラガマにつきましては、今回何の知識もないまま中に入りましたので、私が目で見た範囲の内容しか紹介していません。当時は病院分室として利用されていた程ですので、ご指摘の通りガマの中には様々な施設が存在していたかも知れません。
ただブログにも書きましたが、中は暗く蒸し暑く、本当に居心地の悪いところでした。このような中で過ごさなければならなかった方々が居た事実は忘れてはいけないと思います。
「南冥の塔」と「轟の壕」につきましては、すぐにという訳ではありませんが、機会を見つけ行ってみたいと思います。ご意見ありがとうございました。
Posted by はじめ at 2007年08月23日 00:45
コープの平和学習で
糸数アブチラガマに2回ほど行きました。
ガマを出ると
重い足どりや肩にドーンと重いものがかぶさり、胸が締め付けられました。
真っ暗中で、平和ガイドの方々の説明は
今でも鮮明に覚えています。
昨年は石川の命しぬじガマへ入りました。
糸数アブチラガマに2回ほど行きました。
ガマを出ると
重い足どりや肩にドーンと重いものがかぶさり、胸が締め付けられました。
真っ暗中で、平和ガイドの方々の説明は
今でも鮮明に覚えています。
昨年は石川の命しぬじガマへ入りました。
Posted by かすみそう at 2007年11月22日 21:03
at 2007年11月22日 21:03
 at 2007年11月22日 21:03
at 2007年11月22日 21:03
かすみそうさんこんばんは。
あのガマは何も知らないまま中に入ったのですが、出てきたときは本当に足取りが重かったです。
昔、あのガマの中の風景はどうだったんだろう、と考えると辛くなってきます。
もう、あのガマを使うことのない世の中になって欲しいと思います。
あのガマは何も知らないまま中に入ったのですが、出てきたときは本当に足取りが重かったです。
昔、あのガマの中の風景はどうだったんだろう、と考えると辛くなってきます。
もう、あのガマを使うことのない世の中になって欲しいと思います。
Posted by はじめ at 2007年11月22日 23:01
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。