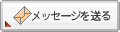沖縄の風景:読者登録
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
沖縄の風景:ブログ検索
沖縄の風景:最近の記事
沖縄の風景:カテゴリー
◆沖縄の風景:全般 (0)
└
イベント・お知らせ (219)
└
お世話になってます (36)
└
深い話 (16)
└
コレやりたい! (9)
└
タメになる?話 (14)
└
ホテル・宿の情報 (27)
└
本の感想 (35)
└
気になるモノ (5)
└
笑える話 (28)
└
雑談 (78)
└
どうでもいい話 (17)
◆沖縄の風景:本島北部 (0)
└
名護市 (14)
└
国頭村 (6)
└
大宜味村 (4)
└
東村 (3)
└
今帰仁村 (44)
└
本部町 (20)
└
恩納村 (25)
└
宜野座村 (2)
└
金武町 (6)
└
伊江村 (27)
└
伊平屋村 (38)
└
伊是名村 (15)
◆沖縄の風景:本島中部 (0)
└
宜野湾市 (40)
└
沖縄市 (35)
└
うるま市 (37)
└
読谷村 (13)
└
嘉手納町 (25)
└
北谷町 (16)
└
北中城村 (33)
└
中城村 (23)
└
西原町 (12)
◆沖縄の風景:本島南部 (0)
└
那覇市 (163)
└
浦添市 (17)
└
糸満市 (9)
└
豊見城市 (8)
└
南城市 (51)
└
与那原町 (1)
└
南風原町 (18)
└
渡嘉敷村 (14)
└
座間味村 (12)
└
粟国村 (49)
└
渡名喜村 (20)
└
南大東村 (24)
└
北大東村 (39)
└
久米島町 (25)
└
八重瀬町 (13)
◆沖縄の風景:宮古 (0)
└
宮古島市 (132)
└
宮古島市伊良部 (38)
└
多良間村 (15)
◆沖縄の風景:八重山 (0)
└
石垣市 (20)
└
竹富町 (26)
└
与那国町 (59)
◆沖縄の風景?:県外 (0)
└
東京都 (82)
└
神奈川県 (22)
└
大阪府 (6)
└
京都府 (2)
└
兵庫県 (10)
└
山口県 (2)
└
福岡県 (20)
└
佐賀県 (11)
└
長崎県 (19)
└
熊本県 (6)
└
大分県 (6)
└
宮崎県 (6)
└
鹿児島県 (2)
└
グァム (6)
└
香港 (16)
沖縄の風景:コメント
沖縄の風景 はじめ / 県営南風原団地建替工事(第2・・・
県営南風原団地建替工事(第2期) / 県営南風原団地建替工事(第2・・・
檸檬 / さわふじの風景
沖縄の風景 はじめ / 安国山樹華木之記碑、南風原・・・
美江 / 安国山樹華木之記碑、南風原・・・
沖縄の風景 はじめ / 安心格安車検、沖縄の車検は・・・
stranger / 安心格安車検、沖縄の車検は・・・
沖縄の風景 はじめ / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
美江 / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
美江 / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
沖縄の風景 はじめ / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
美江 / 竹富島、晴れていれば絶景間・・・
沖縄の風景 はじめ / 竹富島、オシャレな外観の竹・・・
美江 / 竹富島、オシャレな外観の竹・・・
沖縄の風景 はじめ / 石垣港離島ターミナルから竹・・・
沖縄の風景:カウンター
沖縄の風景:タグクラウド
那覇市
宮古島市
モブログ
東京都
与那国町
南城市
今帰仁村
粟国村
宜野湾市
北大東村
うるま市
伊平屋村
沖縄市
琉球ドラゴンプロレス
伊良部島
世界遺産
琉球ドラゴンプロレスリング
北中城村
那覇空港
竹富町
竹富島
伊江村
天然記念物
文化財
石垣市
拝所
南大東村
恩納村
沖縄キャンプ
台風
今帰仁城跡
久米島町
鍾乳洞
嘉手納町
南風原町
本部町
首里城公園
渡名喜村
琉球石灰岩
中城村
台風対策
台風情報
パワースポット
テオ・ヤンセン
ビーチアニマル
宝当神社
玉泉洞
渡嘉敷村
香港
福岡県
伊良部大橋
首里城
名護市
浦添市
北谷町
琉球ゴールデンキングス
ユネスコ
天気予報
伊是名村
国際通り
プロ野球
栗城史多
宿泊施設
長崎市
佐賀県
Dr.コトー診療所
宝くじ
座間味村
池間島
八重瀬町
沖縄県立博物館
重要文化財
有形文化財
さしみ屋
刺身屋
台風予報
ネーブルカデナアリーナ
ストランドビースト
テオヤンセン
読谷村
古宇利島
神奈川県
多良間村
さしみ屋のお告げ
沖縄県
西原町
日本トランスオーシャン航空
宮古島
奥武島
琉球キングス
琉球王国のグスク及び関連遺産群
豊見城市
粟国の塩
広島東洋カープ
興南高校
グルクンマスク
琉球ドラゴンチャンプルー
沖縄県立美術館
観光名所
湧水
沖縄の風景:過去記事
沖縄陸軍病院南風原壕で思い出した事
南風原町にある黄金森(こがねもり)野球場の裏手には、戦時中病院として使用された沖縄陸軍病院南風原壕跡があります。

黄金森陸上競技場の駐車場にある小さな案内板を目印に壕跡へ向かいます。入口までは250m程度歩きます。

壕跡へ向かう途中、20号壕出口の前を通ります。壕入口に向かうため、更に奥へ歩いていきます。

壕入口を目指し、遊歩道を歩いていきます。

2007年6月より一般公開が始まった20号壕の入口に着きました。

 「沖縄陸軍病院南風原(はえばる)壕群20号」 - 現地の看板より引用。
「沖縄陸軍病院南風原(はえばる)壕群20号」 - 現地の看板より引用。
20号は第二外科の中心的な壕で、患者の病室、手術場、勤務者室として使用されました。北側に隣接する19号や南側に隣接する21号と中央部で連結した貫通壕でした。
西口から十字路までの左側壁沿いには軍医と衛生兵、看護婦用の二段ベットが設けられ、薬品箱や医療器具などが置かれていました。4月中旬からは中央部の十字路が手術場となり、ランプのほの暗い灯りで、麻酔なしの手術が行われたのです。それは傷口からの炎症を防ぐため手足を切断する患部手術が殆どでした。十字路から21号につながる通路には戸板が並べられ、それが女子学徒たちの休憩所でした。十字路から東口までの右側壁沿いには幅約90センチメートルの棚が二段あり、入院患者のベットとして使われていました。
気管を切開し、喉からピューピューと息がもれる患者、下あごのない患者、火炎放射器で全身を焼かれた患者など、直視出来ないほどの重症を負った患者が収容されていました。
1994年から行われた考古学的発掘調査によって、壕の長さが約70m、高さほぼ1.8m、床幅1.8mで構築されたことや、東口外側で地中に隠すように埋められた多数の医薬品類が確認されています。壕の壁や天井にはツルハシで掘った跡が残り、床面にはほぼ90cmおきに坑木を設置する柱穴があります。坑木の一部は焼けて炭化していますが、現在も残っています。壁や天井も黒く焼けこげており、これは病院の南部撤退後、米軍の火炎放射攻撃によって壕内が火災状態になったためと見られています。なお十字路付近の天井部分には、朝鮮人兵士が書いたと考えられる文字が刻まれています。
- 南風原文化センター 2007年
壕の中を見学しようと思い、20号壕入口の受付を訪ねたのですが人影がありません。受付の案内をよく見てみると、内部の見学は完全予約制とのことでした。私は予約なしで壕を訪ねたため、今回は内部の様子を知ることは出来ませんでした。
仕方がないので、20号壕入口の案内板にある内部の写真を撮影しました。






20号壕入口の側には憲法九条の碑が建てられています。

近くに24号壕の入口がありましたが、まだ整備されていないので一般公開されていないようです。

20号壕入口にある看板の説明文を読んでいたとき、昔のことを思い出していました。
私がまだ小さな頃、実家の近くに小さな病院がありました。その病院の先生は小柄で年配の方でしたが、話し方が乱暴で対応も荒々しく、何かにつけすぐに注射を打ってくるものですから、子供の私にとっては恐怖以外の何者でもありませんでした。私が何か悪さをした際、親が「○○病院に連れて行って先生に看てもらうよ!」と言うとすぐに泣いて謝ったという程ですから、よほど怖かったのだろうと思います。
子供だったので記憶が曖昧なのですが、先生の口癖は「こんなもの怪我のうちに入らない」で、何で怪我をして病院に来ているのに怪我でないのか、と頭にきたことを覚えています。
後で知ったのですが、先生は元軍医で、戦時中相当な思いをしながら生き残った方だとのことでした。知り合いの話では、先生は滅多に酒を飲まないのだが、飲むと必ず当時のことを思い出していたようで、最後はいつも「助けることが出来ず済まなかった」と号泣していたそうです。子供の頃から怖い人、というイメージしかなかった先生でしたが、その話を初めて聞かされたときは申し訳ない気持ちで一杯でした。
20号壕の出口は黄金森野球場を向いています。彼らには今の世の中がどう見えているのでしょうか。

 沖縄陸軍病院南風原壕の場所はこちら
沖縄陸軍病院南風原壕の場所はこちら
 「沖縄の風景」いかがでしたか?沖縄の人気ブログランキングもよろしく!
「沖縄の風景」いかがでしたか?沖縄の人気ブログランキングもよろしく!
黄金森陸上競技場の駐車場にある小さな案内板を目印に壕跡へ向かいます。入口までは250m程度歩きます。
壕跡へ向かう途中、20号壕出口の前を通ります。壕入口に向かうため、更に奥へ歩いていきます。
壕入口を目指し、遊歩道を歩いていきます。
2007年6月より一般公開が始まった20号壕の入口に着きました。
 「沖縄陸軍病院南風原(はえばる)壕群20号」 - 現地の看板より引用。
「沖縄陸軍病院南風原(はえばる)壕群20号」 - 現地の看板より引用。20号は第二外科の中心的な壕で、患者の病室、手術場、勤務者室として使用されました。北側に隣接する19号や南側に隣接する21号と中央部で連結した貫通壕でした。
西口から十字路までの左側壁沿いには軍医と衛生兵、看護婦用の二段ベットが設けられ、薬品箱や医療器具などが置かれていました。4月中旬からは中央部の十字路が手術場となり、ランプのほの暗い灯りで、麻酔なしの手術が行われたのです。それは傷口からの炎症を防ぐため手足を切断する患部手術が殆どでした。十字路から21号につながる通路には戸板が並べられ、それが女子学徒たちの休憩所でした。十字路から東口までの右側壁沿いには幅約90センチメートルの棚が二段あり、入院患者のベットとして使われていました。
気管を切開し、喉からピューピューと息がもれる患者、下あごのない患者、火炎放射器で全身を焼かれた患者など、直視出来ないほどの重症を負った患者が収容されていました。
1994年から行われた考古学的発掘調査によって、壕の長さが約70m、高さほぼ1.8m、床幅1.8mで構築されたことや、東口外側で地中に隠すように埋められた多数の医薬品類が確認されています。壕の壁や天井にはツルハシで掘った跡が残り、床面にはほぼ90cmおきに坑木を設置する柱穴があります。坑木の一部は焼けて炭化していますが、現在も残っています。壁や天井も黒く焼けこげており、これは病院の南部撤退後、米軍の火炎放射攻撃によって壕内が火災状態になったためと見られています。なお十字路付近の天井部分には、朝鮮人兵士が書いたと考えられる文字が刻まれています。
- 南風原文化センター 2007年
壕の中を見学しようと思い、20号壕入口の受付を訪ねたのですが人影がありません。受付の案内をよく見てみると、内部の見学は完全予約制とのことでした。私は予約なしで壕を訪ねたため、今回は内部の様子を知ることは出来ませんでした。
仕方がないので、20号壕入口の案内板にある内部の写真を撮影しました。
20号壕入口の側には憲法九条の碑が建てられています。
近くに24号壕の入口がありましたが、まだ整備されていないので一般公開されていないようです。
20号壕入口にある看板の説明文を読んでいたとき、昔のことを思い出していました。
私がまだ小さな頃、実家の近くに小さな病院がありました。その病院の先生は小柄で年配の方でしたが、話し方が乱暴で対応も荒々しく、何かにつけすぐに注射を打ってくるものですから、子供の私にとっては恐怖以外の何者でもありませんでした。私が何か悪さをした際、親が「○○病院に連れて行って先生に看てもらうよ!」と言うとすぐに泣いて謝ったという程ですから、よほど怖かったのだろうと思います。
子供だったので記憶が曖昧なのですが、先生の口癖は「こんなもの怪我のうちに入らない」で、何で怪我をして病院に来ているのに怪我でないのか、と頭にきたことを覚えています。
後で知ったのですが、先生は元軍医で、戦時中相当な思いをしながら生き残った方だとのことでした。知り合いの話では、先生は滅多に酒を飲まないのだが、飲むと必ず当時のことを思い出していたようで、最後はいつも「助けることが出来ず済まなかった」と号泣していたそうです。子供の頃から怖い人、というイメージしかなかった先生でしたが、その話を初めて聞かされたときは申し訳ない気持ちで一杯でした。
20号壕の出口は黄金森野球場を向いています。彼らには今の世の中がどう見えているのでしょうか。
 沖縄陸軍病院南風原壕の場所はこちら
沖縄陸軍病院南風原壕の場所はこちら 「沖縄の風景」いかがでしたか?沖縄の人気ブログランキングもよろしく!
「沖縄の風景」いかがでしたか?沖縄の人気ブログランキングもよろしく!この記事へのコメント
野戦病院の跡地ですか。戦跡めぐりは、いつ見ても胸が締め付けられます。ひめゆりの方たちも、こちらで負傷兵の看病をなさったんですよね。 戦争経験者にとっては、足を踏み入れたくない場所でしょう。
Posted by 美江 at 2007年09月10日 15:17
at 2007年09月10日 15:17
 at 2007年09月10日 15:17
at 2007年09月10日 15:17
野戦病院の跡地ですか。戦跡めぐりは、いつ見ても胸が締め付けられます。ひめゆりの方たちも、こちらで負傷兵の看病をなさったんですよね。 戦争経験者にとっては、足を踏み入れたくない場所でしょう。
Posted by 美江 at 2007年09月10日 15:18
at 2007年09月10日 15:18
 at 2007年09月10日 15:18
at 2007年09月10日 15:18
美江さんこんにちは。
聞いたところでは、現在公開されている20号壕の他にも数箇所倒壊している壕があり、そこからは未だに人骨が発見されるのだそうです。
60年以上経っているはずなのに、まだ戦争は終わっていないようにも思えます。
聞いたところでは、現在公開されている20号壕の他にも数箇所倒壊している壕があり、そこからは未だに人骨が発見されるのだそうです。
60年以上経っているはずなのに、まだ戦争は終わっていないようにも思えます。
Posted by はじめ at 2007年09月11日 14:23
ちょうどここを紹介してほしいと思っていたのでとても嬉しく思います。
ここ何年も黄金森を探索し壕入り口や飯あげの道を探し回ったとをおもいだします。
壕内の図面などは、文化センターで手に入れてますが、公開の計画があることは知っていたので、毎年、何時になるかと南風原役場へ問い合わせていました。
6月から予約して9月1日にいってきました。
内部は、砂岩に近く落盤のおそれの比較的少ない部分をまず公開したとおもわれます。
ほんの数十メートルしかありませんが他の戦跡を訪れてきた方には、ぜひ見学してほしいところです。
ひめゆり学徒隊や32軍、陸軍病院や県司令部の動きがしのばれる重要なポイントです。
うちなんちゅうの方には、辛いことも多いのですが、事実を知ることは、とても重要です。
糸数壕とは違いLEDの懐中電灯をただで貸してもらえます。予約でしか入れませんがガイドさんがつきます。私たちの時は、ガイドさんから「平和のため」という気持ちが伝わり共感をいたしました。
ひめゆりの塔ほど派手ではありませんが皆さんも訪れてみて下さい。
ここ何年も黄金森を探索し壕入り口や飯あげの道を探し回ったとをおもいだします。
壕内の図面などは、文化センターで手に入れてますが、公開の計画があることは知っていたので、毎年、何時になるかと南風原役場へ問い合わせていました。
6月から予約して9月1日にいってきました。
内部は、砂岩に近く落盤のおそれの比較的少ない部分をまず公開したとおもわれます。
ほんの数十メートルしかありませんが他の戦跡を訪れてきた方には、ぜひ見学してほしいところです。
ひめゆり学徒隊や32軍、陸軍病院や県司令部の動きがしのばれる重要なポイントです。
うちなんちゅうの方には、辛いことも多いのですが、事実を知ることは、とても重要です。
糸数壕とは違いLEDの懐中電灯をただで貸してもらえます。予約でしか入れませんがガイドさんがつきます。私たちの時は、ガイドさんから「平和のため」という気持ちが伝わり共感をいたしました。
ひめゆりの塔ほど派手ではありませんが皆さんも訪れてみて下さい。
Posted by kenshin at 2007年09月12日 19:25
kenshinさんこんばんは。
今回、予約なしで現地を訪れたものですから、中の様子は看板の写真で確認したのみです。20号、24号の他にも数カ所、壕の調査が行われているようなのですが、現在どのような状況なのかよく分かりません。地盤が弱いということであれば、安全のため今後公開されるかどうかも不明ですね。
目立たない場所にある戦跡ですが、悲しい歴史を持つ場所です。
今回、予約なしで現地を訪れたものですから、中の様子は看板の写真で確認したのみです。20号、24号の他にも数カ所、壕の調査が行われているようなのですが、現在どのような状況なのかよく分かりません。地盤が弱いということであれば、安全のため今後公開されるかどうかも不明ですね。
目立たない場所にある戦跡ですが、悲しい歴史を持つ場所です。
Posted by はじめ at 2007年09月13日 01:33
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。